こんにちは、公認心理師のピュシカです。
今年は、「街中にクマが出没した」というニュースを毎日のように観ます。
私自身も、帰り道で“クマ出没による通行止め”に遭い、渋滞でしばらく動けなくなりました。こんなに寒くなったのに、近所での目撃情報も、ほぼ毎日です。
「クマが出ています」と聞いても、どこか現実感が薄いように感じることがあります。
実際、人の心には、危険なものを無害に見せようとする働きがあり、ニュースで見るクマをつい“プーさんのような存在”として捉える人もいます。これは無意識に、自分の不安を和らげようとする反応です。
こうした“イメージの書き換え”は、自分の不安を和らげるために無意識に起きることがあります。
それでも、ニュースで見る出来事が、突然“自分の生活圏”のすぐ近くまで迫ってくる。その瞬間、人は初めて「これは本当に危険かもしれない」とリアルに感じ始めます。
この記事では、
✔「自分は大丈夫」と思ってしまう心理
✔被害者を責めてしまう、クマをプーさんだと思う“無意識の思い込み”
✔過剰に怖がらず、油断もしないための対処法
を心理学の視点からわかりやすくお伝えします。
1. 正常性バイアス――“いつも通り”を守りたい心の働き
まず最初に知っておきたいのは、正常性バイアスです。
これは、非常時にも「まだ大丈夫」「たいしたことはない」と感じてしまう心の傾向のことです。
たとえば…
•火災報知器が鳴っても、「誤作動かも」と避難しない
•大きな地震のあとでも、「もう揺れないだろう」と動かない
こうした反応は、大災害が起きたあとに観ると不思議と思うかもしれませんが、自然な反応です。
もし日常の小さな異変すべてに敏感に反応していたら、私たちの心は不安でいっぱいになります。
だから脳は、 “異常を正常に見せて、こころを守ろうとする”という防衛反応を働かせます。
ただし、この反応が強すぎると、現実のリスクを見落としてしまう危険があります。
そんな時は、「私は安心したいだけかもしれない」と立ち止まることが大切です。
感情ではなく“事実”を確認する習慣が、冷静で現実的な判断につながっていきます。

2. 楽観バイアス――「未来は自分だけはうまくいく」と思う心理
次に知っておきたいのが、楽観バイアスです。
これは、
「自分は事故に遭わない」
「自分は病気にならない」
「自分の町にクマは出ない」
と、“自分だけは良い結果になるだろう”と信じてしまう傾向です。実はこの楽観も、日常を生きるうえで必要なものでもあります。
ずっと不安に押しつぶされていては、前に進むことができなくなるからです。しかし、楽観バイアスが強すぎると…このくらい大丈夫だろうと
•山道にゴミを放置する
•「近道だから」と立ち入り禁止の道に入る
•自分だけは大丈夫
と思ってしまうなど、リスクを軽視する行動につながることがあります。
ここで大切な視点が、「安心感」と「安全感」は別物ということ。
「慣れている道だから安心」 → これは“安心感(気持ち)”
「最近クマが出ているから別の道にしよう」 → これは“安全感(事実)”
安心している=安全であるとは限らないのです。
日常の中で、「私は安心したいだけ?それとも安全を確かめている?」と問いかけるだけで、リスク判断の精度は大きく変わります。

3. リスク認知バイアス――“近く”と“遠く”の危険の感じ方
人は、危険を“距離”で判断しがちです。これをリスク認知バイアスと言います。
たとえば…
被害が近い地域の人 は、 危険をリアルに感じやすい
地理的に遠い人 は、「自分には関係ない」と感じやすい
また、経験していないことほど“どこか他人事”に感じやすくなります。
これはクマに限らず、
•交通事故
•災害
•健康のリスク
すべてに共通します。
ニュースを見て怖いと思うのに、日常の備えはつい後回しにしてしまう。これは“危険を軽く見ている”のではなく、 「見えないリスクほど実感しづらい」という心の癖が働いているだけなのです。
この仕組みを知るだけで、自分や周りの行動を責めすぎず、冷静にバランスを取れるようになっていきます。

4. 公正世界仮説――“被害者には落ち度がある、クマが可哀想”と思ってしまう無意識
もうひとつ、人の判断を左右するのが公正世界仮説という考え方です。これは、「世の中は基本的に公平で、悪いことは悪い人に起きる」という無意識の思い込みです。
この信念は、日常では心を安定させる“支え”になります。しかし強く働くと、
•「自分はマナーを守っているから大丈夫」
•「被害に遭うのは注意不足の人」
という考えにつながってしまうことがあります。
さらに、この思い込みは被害者に対しても向けられ、
•「そんな場所に行くから被害者が悪い」
•「気をつけてなかったんじゃないか」
•「クマは悪くない」
という評価になってしまうことも。
これは、「自分は同じ目に遭いたくない」という心の防衛反応なのです。でも現実は、誰にでも想定外のことが起こり得ます。
大切なのは、
不公平な出来事も起こり得ると知ること
“可能性”を想定した行動をとること
被害者を責めない心を持つこと
です。
そしてその優しさは、めぐりめぐってあなたと周りの人も守る力になっていきます。

5. 過剰に怖がらず、油断もしないために――冷静なリスク認知の育て方
リスクと向き合う時に大切なのは、「想像ではなく事実を見ること」です。
✔SNSの噂より、公式の発表を確認する
✔断片的な映像より、正確な情報を見る
“怖い”より“知る”を優先すると、心は落ち着きを取り戻します。
クマの出没情報は各地域で名称は違いますが、くまっぷ、クマダズ、ひぐまっぷなどで確認できます。出没が近かったら、怖いのですが、でも必要以上に怖がらず、過小評価もせず、冷静に注意を払うことが大切です。
お互いに気をつけましょうね。

おわりに ― 私たちは不安と安心のあいだで生きている
“自分は大丈夫”と思いたい気持ちも“悪いことは悪い人に起こる”と思いたい気持ちも、根底には 「安心したい」という願いがあります。
人は誰でも、不安と安心のあいだを行き来しながら生きています。
その揺れの中で、ほんの少し立ち止まって、「事実はどうだろう?」と見つめられるだけで、自分も周りも守る行動へつながっていきます。
最後に、
日々、熊の出没から命懸けで住民を守るために活動されている皆さまへ、
深い敬意と感謝を申し上げます。ご無事を切に願っております。
そして、被害に遭われた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
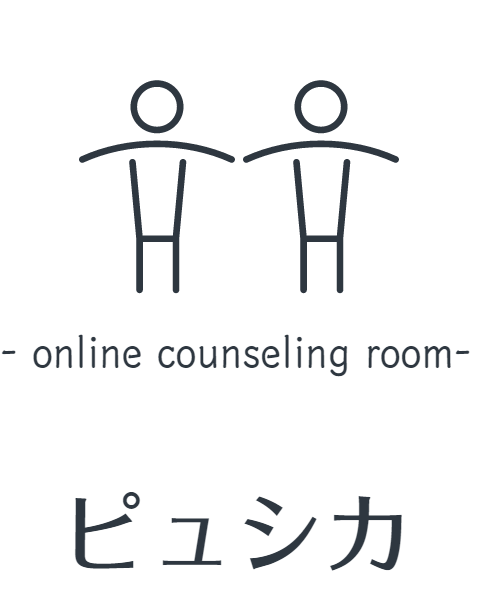
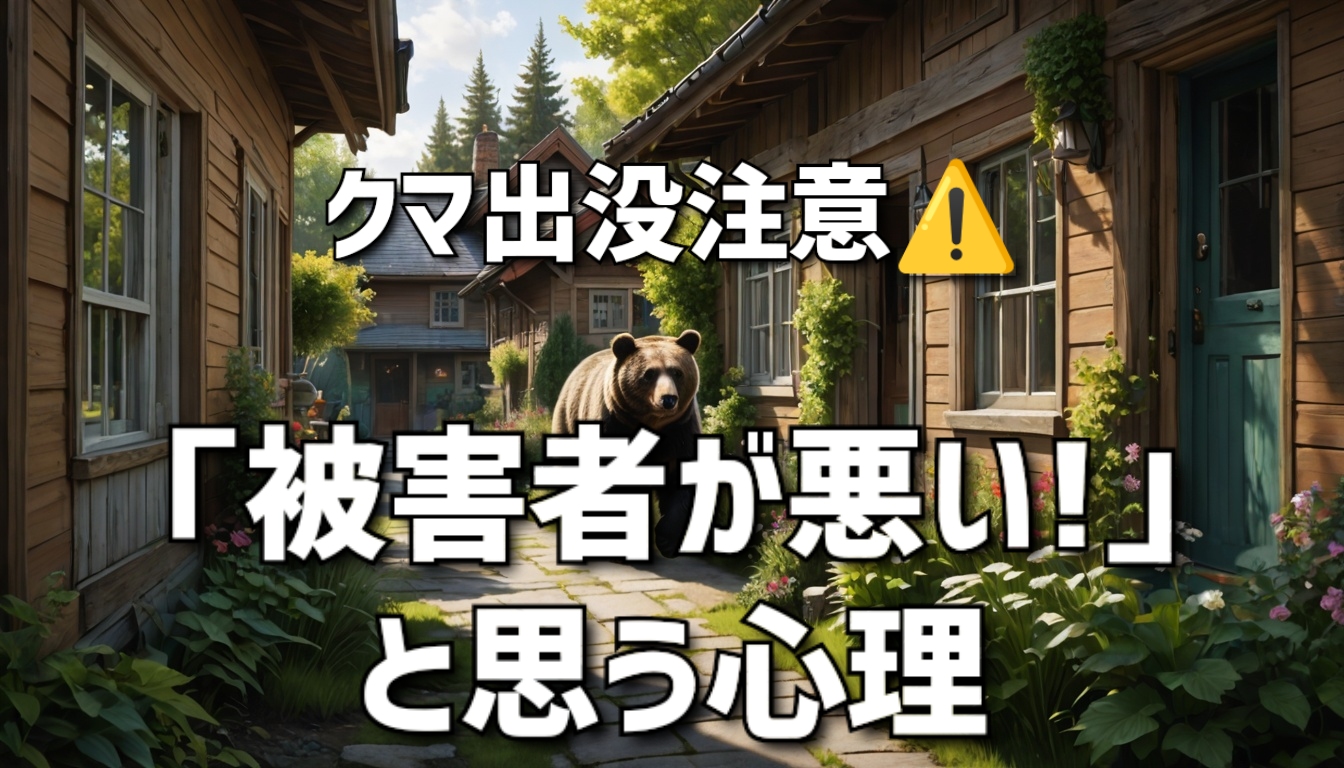
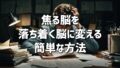

コメント