こんにちは、公認心理師のピュシカです。
何かに追われているわけでもないのに、
なぜか心がざわついて落ち着かないことは、ありませんか?
メールの通知、会話の沈黙、誰かの一言。
小さな出来事がきっかけで、心のスイッチが一気に“焦りモード”に入ることがあります。
「落ち着こう」と思えば思うほど、もっと焦ってしまう。
そんな時、人は“理屈では止められない焦り”に飲み込まれてしまいます。
実は、焦りには“脳の仕組み”があります。
この記事では、焦りが生まれるメカニズムと、落ち着きを取り戻すための方法をお伝えします。
焦りは「危険信号」ではなく「誠実信号」

焦りを感じると、つい「何やってるんだ!」「何でこんなことできないんだ!」などと責めてしまいがちですよね。
でも心理学的に見ると、焦りは“危険信号”というより“誠実信号”です。
焦っている時、脳は「守らなきゃ」とあなたを守ろうとしています。
たとえば、
•ミスを避けたい
•遅れたくない
•人に迷惑をかけたくない
そんな気持ちがあるからこそ、脳がフル回転して“今すぐ動いて”と指令を出します。
つまり焦りは、あなたが「きちんとしたい」と強く思っている状態。
真面目さや責任感の裏返しです。
焦っているとき、脳の中で起きていること
焦りのとき、脳内では“アクセルとブレーキ”が同時に踏まれています。
「早くしなきゃ」というアクセルと、
「間違えたくない」というブレーキ。
両方が同時に作動することで、頭が真っ白になったり、
思考が空回りしてしまうんです。
この状態では、気合いや根性でコントロールするのは難しい。
焦りは「気持ちの問題」ではなく、脳の反応なのです。
焦りに強い人の共通点
焦りやすい人とそうでない人の違いは、「焦りを止めようとするか」「気づこうとするか」にあります。
焦りに強い人は、焦りを“敵”にせず、“サイン”として受け取っています。
「今、焦っているな」
「少し急ぎすぎているかも」と気づくことで、脳の反応が落ち着くからです。
焦りを感じた瞬間、まず深呼吸をひとつ。
そして焦っている自分に気づくこと。
たったそれだけで、脳の緊張は少しずつほどけていきます。

焦りをためにくい人がしている習慣
焦りは“発作的に起こるもの”と思われがちですが、実は「日常の積み重ね」で変わります。
焦りをためにくい人が意識しているのは、次の3つです。
•余白の時間をつくる
1日の中で、何もしない時間を数分でも持つ。
脳が「今は追われていない」と認識すると、安心が積み重なります。
•人と比べる情報を減らす
SNSや他人の成果を見るほど、焦りは強まります。
“自分のペース”を守る勇気が、心の安定を生みます。
•朝に「今日の優先1つ」を決める
焦りの多くは「やることが多すぎる」混乱から。
朝に“これだけは”を決めておくことで、1日の迷いが減ります。

焦りをやさしく手放すために
焦りを抑えようとすると、余計に苦しくなります。
でも“気づいて受けとめる”だけなら、今すぐにできます。
焦っているときほど、「自分は今、真剣に向き合っているんだ」と思い出してみてください。
焦りの中には、あなたの誠実さや、誰かを思う気持ちが隠れています。
その焦りを敵にせず、味方にしてあげる。
それが「焦る脳を落ち着く脳に変える」最初の一歩です。
実際に心を落ち着かせる3つの具体的な方法については、
こちらの動画で詳しくお話ししています。
「焦る脳を、落ち着く脳に変える方法」👇
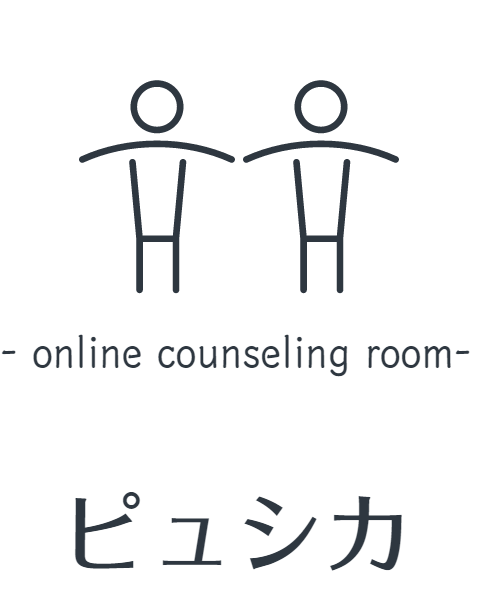
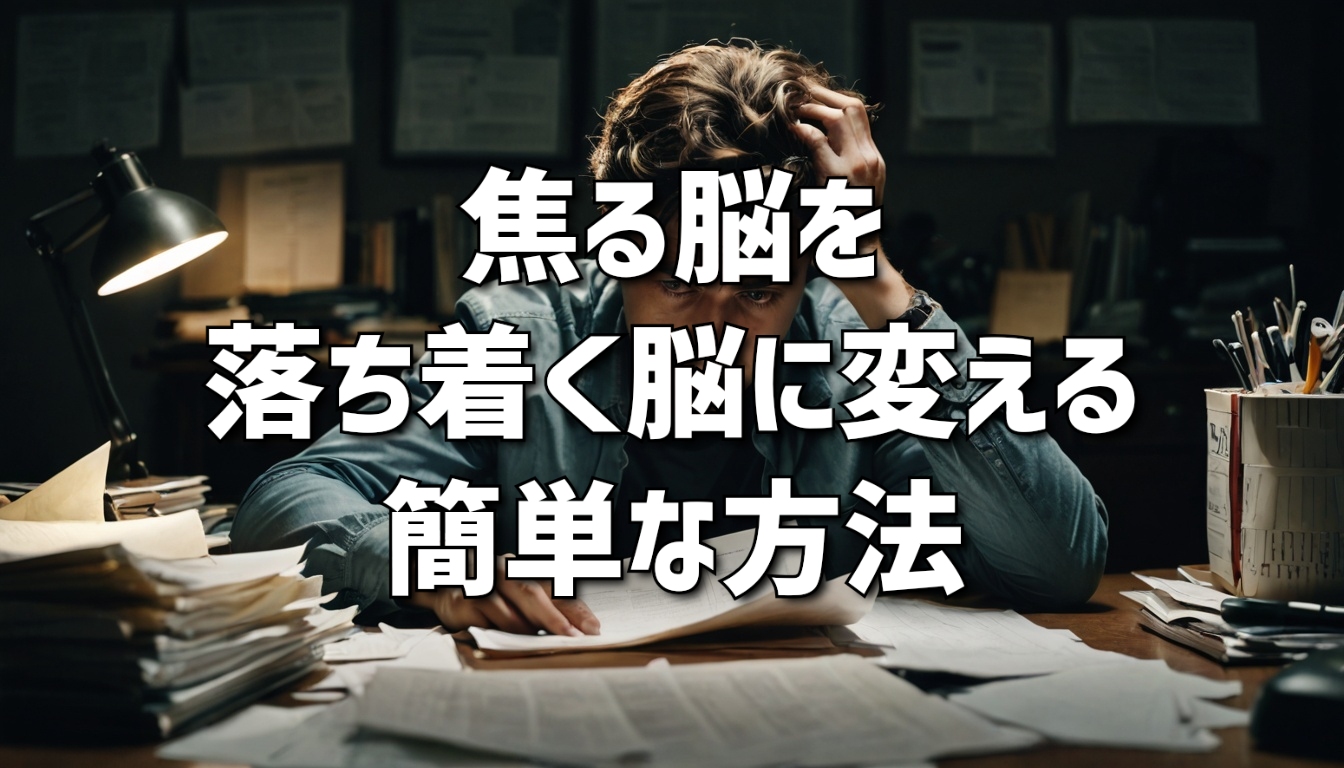
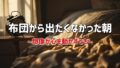
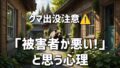
コメント