「昼間の出来事、もう考えないようにしようと思ってるのに、気づくとまた思い出してる」「終わったことなのに、何度もよみがえってしまう…」そんなふうに、嫌な記憶がなかなか手放せずに困ってしまうことはありませんか?
私も忘れたい嫌なことを、気づくと考えてしまっていて家のことがはかどらないなんてことがありました。
ここでいう“忘れる”とは、記憶を消すという意味ではありません。
思い出しても心が大きく揺れなくなること、日常生活に支障が出ない心の状態をつくるということです。
この記事では、心理学の知識をもとに、脳や心のクセを整えるための実践的な3ステップを紹介します。
さらに、記憶との付き合い方を変えるための1つの視点もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
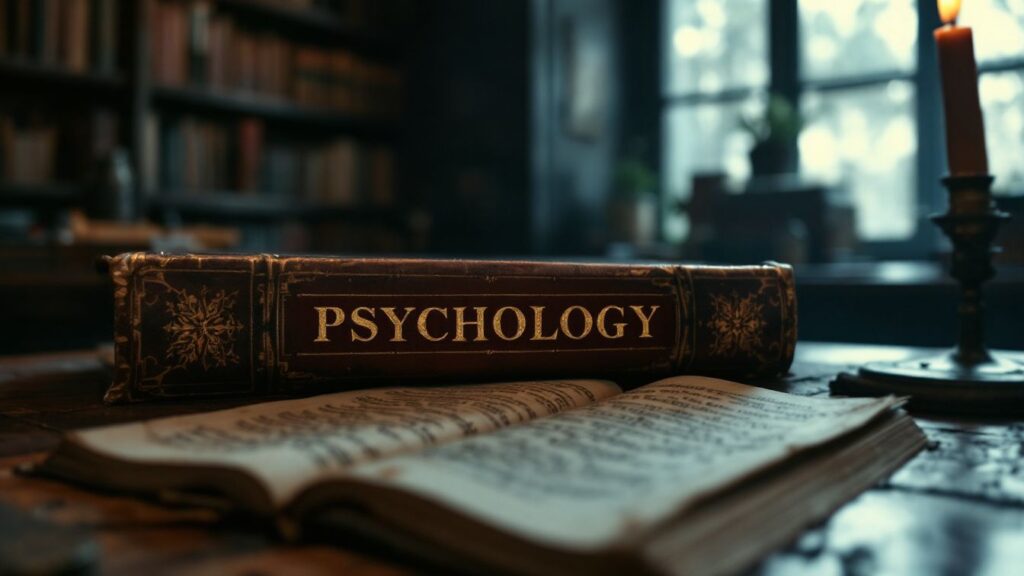
なぜ嫌なことほど忘れにくいのか?
嫌な記憶や忘れたい記憶は、なぜ強く残ってしまうのでしょうか?それには、脳の働きが深く関係しています。
脳には「扁桃体(へんとうたい)」という、感情の記憶に関わる部分があります。危険や不快な体験があると、扁桃体が「これは重要な情報だ」と判断し、記憶をより強く脳に刻み込みます。
そして、それを繰り返し思い出してしまうのは、「同じことを繰り返さないようにしよう」という防衛反応なのです。
つまり、忘れられないのは脳の働きによるごく自然な現象です。

「忘れよう」とするほど思い出してしまう理由
実は、「忘れよう」とすればするほど、逆に思い出しやすくなるという心理的な仕組みがあります。
これは、アメリカの心理学者ダニエル・ウェグナーが提唱した「皮肉過程理論(Ironic Process Theory)」によって説明できます。
彼の有名な実験のひとつが、「シロクマを考えないでください」という指示を与えたところ、参加者はむしろ何度もシロクマを思い浮かべてしまった、というもの。
これは、脳が次のような2つの処理を同時に行うことで起きます。
1. 「考えないようにする」意識的な抑制
2. 「今、自分は考えていないか?」という監視
この監視のプロセスで、脳は無意識のうちに対象を探しに行ってしまうため、結果として思い出す回数が増えてしまうのです。
「忘れたい!」という強い気持ちが、かえって記憶を呼び起こすトリガーになっている――。これが、私たちがはまりやすい“心のクセ”です。
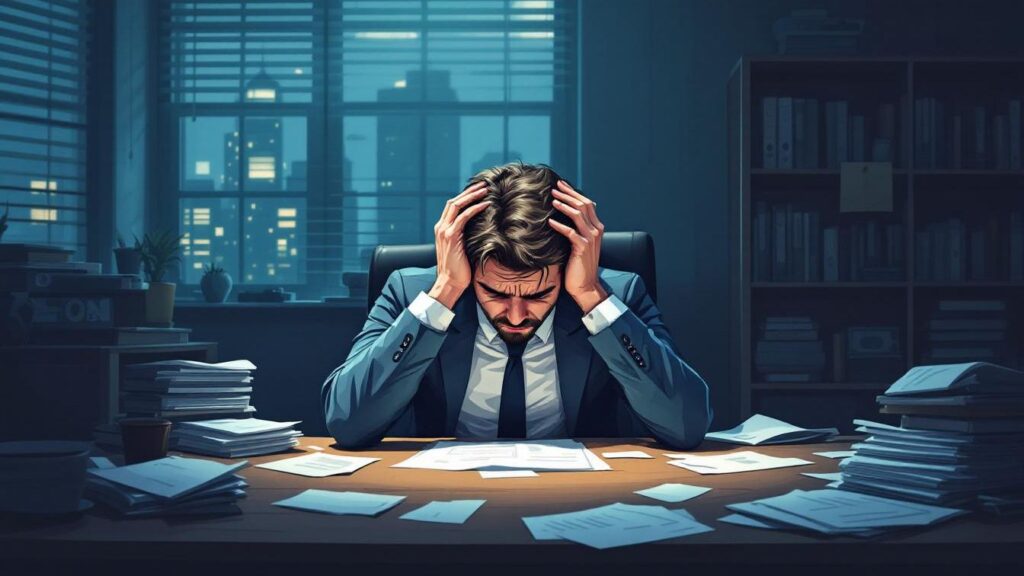
脳と心のクセを整える3つのステップ
ここからは、「忘れたいのに思い出してしまう」状態から少しずつ抜け出すための、具体的な方法を3つご紹介します。
ステップ1~書き出して“外に出す”
頭の中でぐるぐるしている記憶や感情は、紙に書き出すことで整理され、落ち着いていくことがあります。
何が嫌だったのか
そのとき何を感じたのか
今、どんな気持ちが残っているか
思いつくまま、言葉にしてみましょう。
これは心理学で「外在化(externalization)」と呼ばれ、自分の中にある気持ちや記憶を“距離のある対象”として扱えるようになる効果があります。
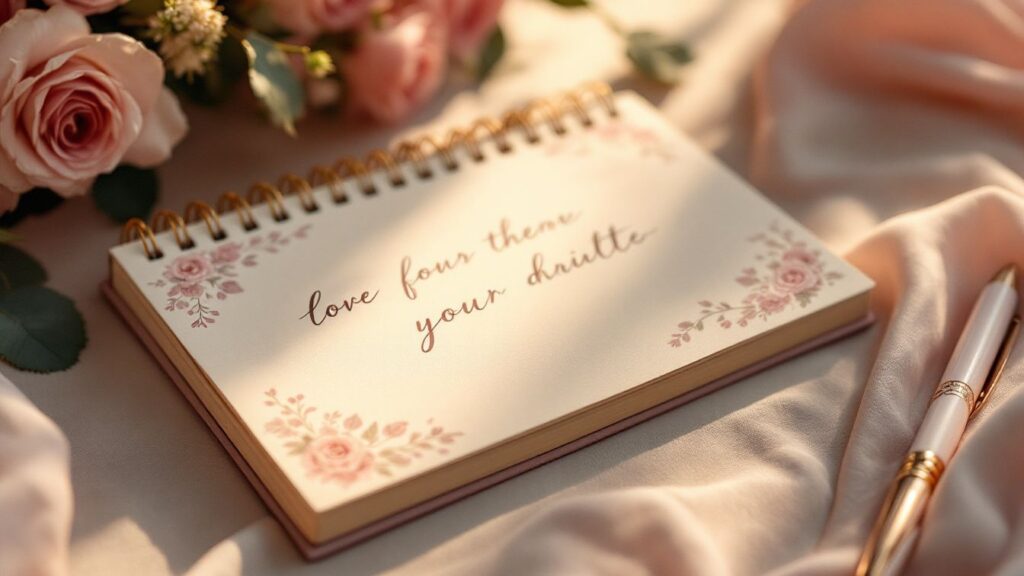
ステップ2~気持ちを否定しない
「いつまでも引きずっていて情けない」「忘れられない自分がダメなんだ」そんなふうに、自分の気持ちにダメ出しをしてしまうことはありませんか?
でも、記憶が残っているのは、それだけ心が一生懸命受け止めた証拠。人間らしい自然な反応です。「まだ思い出す自分も、今の自分の一部なんだな」そう認めることが、心を緩める第一歩になります。
ステップ3~身体から整える
考え続けて頭が疲れてしまったときは、身体の感覚に意識を向けてみることも大切です。
ゆっくり深呼吸する軽くストレッチするお風呂にゆったり浸かる好きな香りをかぐ自然の中を散歩する身体と心はつながっています。
身体がゆるむと、心も自然と落ち着いていくものです。

記憶の意味を再構成する――新たな視点
「もう済んだことなのに、どうしても記憶が残ってしまう」そうした記憶に対しては、“意味づけ”を変えることで、心の重さが軽くなることがあります。
これは、心理学で「ナラティブ・アプローチ」や「リフレーミング」と呼ばれる考え方に基づいています。
たとえば…
「あのときの失敗があったから、慎重さを身につけられた」
「あの経験で、人の痛みに気づけるようになった」
「あれを境に、自分にとって本当に大事なことが見えた」
このように、出来事そのものではなく、“その記憶が自分の人生にどう作用したか”を問い直してみることで、記憶の位置づけを“心の中心”から“人生の一部”へと移動させることができます。
記憶が心を支配するのではなく、今の自分が、記憶に意味を与える側になるという発想です。

まとめ
忘れられないのは、脳の自然な防衛反応
「忘れよう」と意識するほど逆に思い出してしまう
書き出し、気持ちの受容、身体へのアプローチで心に余白をつくる
記憶の意味を再構成することで、“人生の一部”として受け止め直せる
嫌なことは、早く忘れたい。でも忘れようとしてしまうと逆効果になって、もっと記憶に残ってしまいます。
無理に忘れようとはせず、思い浮かんだら眺めるだけにしてみましょう。そうすることで、嫌なことに支配されずに過ごすことができます。
思い出しても、もう心が大きく動かない。そんな自分になれる日は、少しずつやってきます。焦らず、少しずつ、自分の心にやさしく向き合っていきましょう。
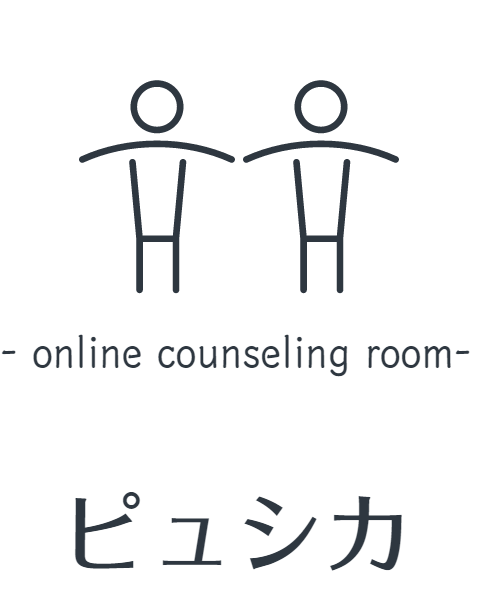
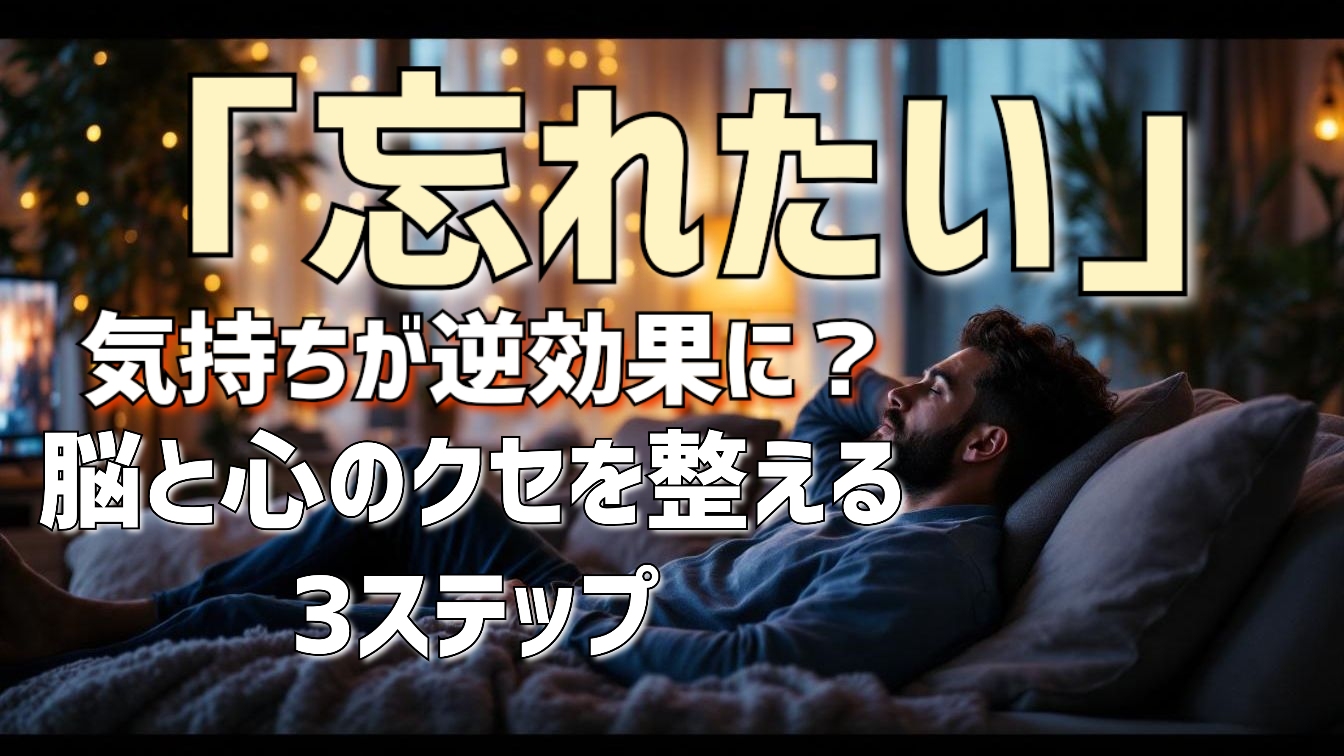
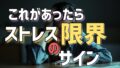
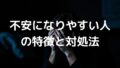
コメント